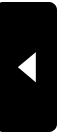2011年08月11日
2011年08月10日
渡り蝶、アサギマダラ
立秋を過ぎたせいか、虫の音が聞こえる。
名前はわからないが、去りゆく夏を惜しんでいるように寂しく鳴いている。キリギリスかもしれないな。君には夏が短すぎたのかい。
草木も眠るはずの丑三つ時である。
夜の蝶ではなく、昼に見た蝶の話をしよう。

その蝶は、戸隠の花と花の間を、優雅に舞っていた。
僕にとっては、はじめて見る珍しいと分類される蝶だった。
林の中はがくあじさいが満開で、蝶は高いところを舞っていた。
そのうち、ひらひらと降りてきて、僕の目の前の花に留まり、至近距離で蜜を吸い始めたのである。
まるで僕の存在を無視するかのように、あるいは誘惑か、幻惑するように、翅を閉じたり、開いたり。
そのときの僕は、これは幻の蝶に違いない、絶滅危惧種の貴重な記録だと、シャッターを押し続けた。


興奮冷めやらぬまま、志の輔目当てに合流した友人に、撮ったばかりの画像を見せた。
「よく見る蝶だね」と一言。
えっ、そうなの。「いいねぇ、いいねぇ」連発の炎天下2時間の撮影は何だったの。
(ここからは天の声:イタリック部分はNATIONAL GEOGRAPHIC 2007年5月号からの引用 )
この蝶は、アサギマダラ。

アサギマダラ(Parantica sita)は、翅を開くと10センチ前後の、比較的大型の蝶である。黒と栗色に縁どられた翅脈の間が、その名の通り浅葱色(淡い水色)に透きとおり、まだら模様になっている。独特の優美な飛びかたをする、なんとも美しい蝶だが、最大の魅力はその行動にある。アサギマダラは日本で唯一知られている、長距離の「渡り」をする蝶なのだ。

この蝶が渡りをするのが確認されたのは、1981年。
移動にかかわる謎の解明には、データを一つひとつ積み重ねていくしかない。その方法が、野生生物の行動や個体数の調査に用いられる「マーキング」である。捕獲した個体に標識をつけて放し、再捕獲により移動の実態を確認する。鳥類やウミガメなどでは標識タグを付けるが、アサギマダラの場合は、油性ペンで翅に直接マークを記入する。この方法は、蝶の飛翔や交尾行動などに影響しないことが、野外での観察からわかっている。

そういえば「マーキングして」と言わんばかり、僕の回りをゆったり旋回していたな。
今では毎年、全国で数万頭にマークがつけられる。再捕獲される確率はせいぜい1%程度だが、それでも年に数百の移動記録が得られ、実態の解明に貢献している。

数万頭、友人がいうように珍しい蝶という訳ではないんだ。蝶って、何頭で数えるんだ。ちょっとびっくり。
長距離移動の事例は、続々と報告されている。2000年には台湾から日本へ、翌年には日本から台湾への移動例が見つかった。さらに2002年には、本州から沖縄県の南大東島へ移動した4例の報告が寄せられた。台湾との間には島々が連なっているが、南大東島へは1000キロもの海を渡るほかない。翌年の南大東島では、本州から5日、四国から3日という高速移動の例もみられた。2005~06年には、小笠原諸島の父島での再捕獲や、長野県から台東沖の島、蘭嶼まで2000キロを超す移動も確認されている。

そうか、蜜をたくさん吸って、長距離移動の燃料補給をしていたんだね。
アサギマダラを見かけることがあったら、そのときは白いタオルを勢いよく回してください。
高いところを飛んでいるアサギマダラも、翅をV字型にしてまっしぐらに降下してきます。
運良く捕まえることができたら、翅に「NAGANO」とマーキングして、リリースしてあげてください。

たぶん、もうそんな機会はないだろうな。
僕にとっては、あのときだけの、特別な蝶との、濃密な時間だった。
名前はわからないが、去りゆく夏を惜しんでいるように寂しく鳴いている。キリギリスかもしれないな。君には夏が短すぎたのかい。
草木も眠るはずの丑三つ時である。
夜の蝶ではなく、昼に見た蝶の話をしよう。
その蝶は、戸隠の花と花の間を、優雅に舞っていた。
僕にとっては、はじめて見る珍しいと分類される蝶だった。
林の中はがくあじさいが満開で、蝶は高いところを舞っていた。
そのうち、ひらひらと降りてきて、僕の目の前の花に留まり、至近距離で蜜を吸い始めたのである。
まるで僕の存在を無視するかのように、あるいは誘惑か、幻惑するように、翅を閉じたり、開いたり。
そのときの僕は、これは幻の蝶に違いない、絶滅危惧種の貴重な記録だと、シャッターを押し続けた。
興奮冷めやらぬまま、志の輔目当てに合流した友人に、撮ったばかりの画像を見せた。
「よく見る蝶だね」と一言。
えっ、そうなの。「いいねぇ、いいねぇ」連発の炎天下2時間の撮影は何だったの。
(ここからは天の声:イタリック部分はNATIONAL GEOGRAPHIC 2007年5月号からの引用 )
この蝶は、アサギマダラ。
アサギマダラ(Parantica sita)は、翅を開くと10センチ前後の、比較的大型の蝶である。黒と栗色に縁どられた翅脈の間が、その名の通り浅葱色(淡い水色)に透きとおり、まだら模様になっている。独特の優美な飛びかたをする、なんとも美しい蝶だが、最大の魅力はその行動にある。アサギマダラは日本で唯一知られている、長距離の「渡り」をする蝶なのだ。
この蝶が渡りをするのが確認されたのは、1981年。
移動にかかわる謎の解明には、データを一つひとつ積み重ねていくしかない。その方法が、野生生物の行動や個体数の調査に用いられる「マーキング」である。捕獲した個体に標識をつけて放し、再捕獲により移動の実態を確認する。鳥類やウミガメなどでは標識タグを付けるが、アサギマダラの場合は、油性ペンで翅に直接マークを記入する。この方法は、蝶の飛翔や交尾行動などに影響しないことが、野外での観察からわかっている。
そういえば「マーキングして」と言わんばかり、僕の回りをゆったり旋回していたな。
今では毎年、全国で数万頭にマークがつけられる。再捕獲される確率はせいぜい1%程度だが、それでも年に数百の移動記録が得られ、実態の解明に貢献している。
数万頭、友人がいうように珍しい蝶という訳ではないんだ。蝶って、何頭で数えるんだ。ちょっとびっくり。
長距離移動の事例は、続々と報告されている。2000年には台湾から日本へ、翌年には日本から台湾への移動例が見つかった。さらに2002年には、本州から沖縄県の南大東島へ移動した4例の報告が寄せられた。台湾との間には島々が連なっているが、南大東島へは1000キロもの海を渡るほかない。翌年の南大東島では、本州から5日、四国から3日という高速移動の例もみられた。2005~06年には、小笠原諸島の父島での再捕獲や、長野県から台東沖の島、蘭嶼まで2000キロを超す移動も確認されている。
そうか、蜜をたくさん吸って、長距離移動の燃料補給をしていたんだね。
アサギマダラを見かけることがあったら、そのときは白いタオルを勢いよく回してください。
高いところを飛んでいるアサギマダラも、翅をV字型にしてまっしぐらに降下してきます。
運良く捕まえることができたら、翅に「NAGANO」とマーキングして、リリースしてあげてください。
たぶん、もうそんな機会はないだろうな。
僕にとっては、あのときだけの、特別な蝶との、濃密な時間だった。
2011年08月09日
熱雷
夏の陽射しで地面が局地的に強く熱せられ、湿気を含んだ下層の空気が上昇して雷雲が発達する。


上空に冷たい空気が流れ込み、大気が不安定な状態になっていると、激しい雷雨になる。


熱雷である。
条件がそろい、志賀、菅平方面は熱雷が闇のなかに閃光を放った。

長野には雷雨はなく、夜空には半月が灯っていた。

上空に冷たい空気が流れ込み、大気が不安定な状態になっていると、激しい雷雨になる。
熱雷である。
条件がそろい、志賀、菅平方面は熱雷が闇のなかに閃光を放った。
長野には雷雨はなく、夜空には半月が灯っていた。
2011年08月08日
蕎麦と落語の幸福な出会い
いま、一番勢いのある二つ目が、長野市の蕎麦屋の高座に上がった。
一人静かに蕎麦を仕込む時、FMから聴こえてくるのが一之輔。
「日本全国、どこへでも参ります」
若い店主はメールで出演を依頼し、それに応えて一之輔はここに来た。

長野市篠ノ井「手打ちそば 桜」
外観は蕎麦屋には見えない。内装も蕎麦屋には見えない。


この蕎麦屋に高座ができた。

ここでは、信州蕎麦は出てこない。
店主が選んだ、旬の蕎麦粉が、店主手打ちの蕎麦になって出てくる。
その中には、信州のものもあるという感じである。
この日の蕎麦は、福井県産。淡く緑がかった細めの蕎麦は、口に含むと甘みと滑りがある。野にある蕎麦の勢いを感じる。
この蕎麦に合わせた日本酒は、中野市・井賀屋酒造場の「岩清水」純米吟醸。この日のために火入れしていない酒を仕入れて、振る舞ってくれた。

落語は、当代若手の筆頭株一之輔。くだんのFM番組、円朝祭を終えて、新幹線で長野まで駆けつける、その心意気や善し。
手打ちそば桜の店主が蕎麦に打ち込む真摯な姿勢は、類となって友を呼んでいる。
長野からの蕎麦屋の挑戦をしばらくの間、羨望とともに応援しようと思う。

Under the Cherry Tree 6th
春風亭一之輔 落語会
8月7日(日)17時30分
・「やかん」春風亭一之輔
・「青菜」春風亭一之輔
蕎麦:福井県産蕎麦粉
日本酒:「岩清水」純米吟醸 中野市・井賀屋酒造場

一人静かに蕎麦を仕込む時、FMから聴こえてくるのが一之輔。
「日本全国、どこへでも参ります」
若い店主はメールで出演を依頼し、それに応えて一之輔はここに来た。
長野市篠ノ井「手打ちそば 桜」
外観は蕎麦屋には見えない。内装も蕎麦屋には見えない。
この蕎麦屋に高座ができた。
ここでは、信州蕎麦は出てこない。
店主が選んだ、旬の蕎麦粉が、店主手打ちの蕎麦になって出てくる。
その中には、信州のものもあるという感じである。
この日の蕎麦は、福井県産。淡く緑がかった細めの蕎麦は、口に含むと甘みと滑りがある。野にある蕎麦の勢いを感じる。
この蕎麦に合わせた日本酒は、中野市・井賀屋酒造場の「岩清水」純米吟醸。この日のために火入れしていない酒を仕入れて、振る舞ってくれた。
落語は、当代若手の筆頭株一之輔。くだんのFM番組、円朝祭を終えて、新幹線で長野まで駆けつける、その心意気や善し。
手打ちそば桜の店主が蕎麦に打ち込む真摯な姿勢は、類となって友を呼んでいる。
長野からの蕎麦屋の挑戦をしばらくの間、羨望とともに応援しようと思う。
Under the Cherry Tree 6th
春風亭一之輔 落語会
8月7日(日)17時30分
・「やかん」春風亭一之輔
・「青菜」春風亭一之輔
蕎麦:福井県産蕎麦粉
日本酒:「岩清水」純米吟醸 中野市・井賀屋酒造場
2011年08月07日
戸隠流、そばの実
このところ、戸隠で蕎麦を食べることはなかった。
善光寺界隈には多くの蕎麦屋があるし、市内でも旨い蕎麦は食べられるようになった。
どうせならと涌井までいくこともある。

鏡池から林の中を曲がりくねって抜けると、茶色い屋根が見えた。
バードラインからのアクセスではなく、そうかこういうルートもあるんだな。旧い友達に出逢ったような感じだ。
蕎麦処 「そばの実」
店の入り口の手水に落ちる水は冷たい。この清涼さがここの蕎麦の決め手だ。

大ざる1枚、注文。

渇いたのどを潤してくれるのが、延命茶。
蕎麦が出来るまでは、戸隠大根の味噌漬け。
窓が広く、店と庭が一体の風景のような開放感がある。
野草や山の花、そして林の中を時折走る車が店の風景の一つになっている。

庭を眺めながら、待つことは少しも苦にならない。


戸隠の水が蕎麦を引き締め、のどごしをよくする。
薬味はなくても、蕎麦の味だけで十分、旨い。
自然の中で自然の恵みを頂戴する。この心持ちが戸隠の蕎麦。
やはり夏の蕎麦は戸隠に限る。

ほっこりと、人心地。「そばの実」
営業時間は11時から16時までと、短い。
善光寺界隈には多くの蕎麦屋があるし、市内でも旨い蕎麦は食べられるようになった。
どうせならと涌井までいくこともある。
鏡池から林の中を曲がりくねって抜けると、茶色い屋根が見えた。
バードラインからのアクセスではなく、そうかこういうルートもあるんだな。旧い友達に出逢ったような感じだ。
蕎麦処 「そばの実」
店の入り口の手水に落ちる水は冷たい。この清涼さがここの蕎麦の決め手だ。
大ざる1枚、注文。
渇いたのどを潤してくれるのが、延命茶。
蕎麦が出来るまでは、戸隠大根の味噌漬け。
窓が広く、店と庭が一体の風景のような開放感がある。
野草や山の花、そして林の中を時折走る車が店の風景の一つになっている。
庭を眺めながら、待つことは少しも苦にならない。
戸隠の水が蕎麦を引き締め、のどごしをよくする。
薬味はなくても、蕎麦の味だけで十分、旨い。
自然の中で自然の恵みを頂戴する。この心持ちが戸隠の蕎麦。
やはり夏の蕎麦は戸隠に限る。
ほっこりと、人心地。「そばの実」
営業時間は11時から16時までと、短い。
2011年08月06日
志の輔、戸隠の夜は熱かった。
戸隠のとんくるりんにはクーラーがない。
観客の期待は熱気となり、200名を越える観客が入ると会場はむし暑い。
網戸を開けて、空気を入れるが、風は流れず効果はない。
虫が何処かから入ってきて、高座の辺りを旋回する。
17回めを迎える「志の輔戸隠の夜」は、過酷な環境で始まった。
処は戸隠そば博物館とんくるりんの2階の大広間である。

1995年、第一回目が開かれたのが「戸隠忍者屋敷」。
その後、宿坊、旅館、個人宅等とところを替えて、とんくるりんに落着いたのが3年前。
夏のとんくるりんはこれが最後でしょう。汗だくだくの志の輔はいう。魂が抜けたようにふらふらと高座を降りる姿をみると、全身全霊で芸に打ち込んでいる志の輔にはクーラーなしの会場は過酷だと思う。
でも、暑かろうが、虫が飛ぼうが、遠くから花火の音が聞こえようが、噺の途中で雨が激しく降り出そうが、そのすべてが戸隠の夜であり、戸隠だけの「志の輔」なのである。

一席目は、自作の「親の顔が見たい」。15年前、子どもが小学3年生の時、こんな子どもになってほしいとつくった噺だそうだ。テストの点数は悪いがしっかり自分の考えが表現できる子ども、それ以上にしっかり自分で考え解答を出す親。人生には○×ではなく、さまざまな解答があるんだ。それを示すのが親の務め。志の輔の教育観。
二席目は会場の照明を落として、会場の暑さを涼しさに替えようと、怪談噺。
でも恐いままで戸隠の闇の中を帰らせませんと、「お菊の皿」。
8枚、9枚。。。10枚、11枚、ええっ。最後はどっと笑わせてくれました。

噺が終わって、深々と頭を下げ、高座を降りるかと思いきや、志の輔は8月開催になった経緯を話し始めた。
被災地での公演を優先したいので、今年の戸隠落語会はやめようかと考えていた。
大震災直後、戸隠の青年団の皆さんが被災地に蕎麦を蒔いた。その蕎麦がまもなく実をつける。その蕎麦で、青年団は被災地で蕎麦を打って、被災地の皆さんに振る舞う。
その話を聞いて、やっぱり戸隠を続けようと、8月の戸隠に来ることを決めた。
まさかクーラーがないとは思ってもみなかった。

志の輔は来週から東北の被災地に行く。
被災地で避難所生活を余儀なくされている方がたを招待し、落語会を開く。
ある避難所では、一日の始めにリーダーが一本締めをするそうだ。
今日一日が希望をもって過ごせるように、避難所全員の心を一つにする「一本締め」。
その話を聞いて、志の輔は、独演会の最後に「一本締め」をするようになった。
「戸隠の皆さん、ガッテンしていただきましたでしょうか。」
大きな拍手の後、志の輔の音頭で、被災地が一日でも一時間でも早く、新しい生活を取り戻すことを祈って、
戸隠の夜に、一本締めが響いた。

第17回 志の輔 戸隠の夜
2011年8月5日(金)18時30分〜21時
・「親の顔が見たい」立川志の輔
・「お菊の皿」立川志の輔
観客の期待は熱気となり、200名を越える観客が入ると会場はむし暑い。
網戸を開けて、空気を入れるが、風は流れず効果はない。
虫が何処かから入ってきて、高座の辺りを旋回する。
17回めを迎える「志の輔戸隠の夜」は、過酷な環境で始まった。
処は戸隠そば博物館とんくるりんの2階の大広間である。
1995年、第一回目が開かれたのが「戸隠忍者屋敷」。
その後、宿坊、旅館、個人宅等とところを替えて、とんくるりんに落着いたのが3年前。
夏のとんくるりんはこれが最後でしょう。汗だくだくの志の輔はいう。魂が抜けたようにふらふらと高座を降りる姿をみると、全身全霊で芸に打ち込んでいる志の輔にはクーラーなしの会場は過酷だと思う。
でも、暑かろうが、虫が飛ぼうが、遠くから花火の音が聞こえようが、噺の途中で雨が激しく降り出そうが、そのすべてが戸隠の夜であり、戸隠だけの「志の輔」なのである。
一席目は、自作の「親の顔が見たい」。15年前、子どもが小学3年生の時、こんな子どもになってほしいとつくった噺だそうだ。テストの点数は悪いがしっかり自分の考えが表現できる子ども、それ以上にしっかり自分で考え解答を出す親。人生には○×ではなく、さまざまな解答があるんだ。それを示すのが親の務め。志の輔の教育観。
二席目は会場の照明を落として、会場の暑さを涼しさに替えようと、怪談噺。
でも恐いままで戸隠の闇の中を帰らせませんと、「お菊の皿」。
8枚、9枚。。。10枚、11枚、ええっ。最後はどっと笑わせてくれました。
噺が終わって、深々と頭を下げ、高座を降りるかと思いきや、志の輔は8月開催になった経緯を話し始めた。
被災地での公演を優先したいので、今年の戸隠落語会はやめようかと考えていた。
大震災直後、戸隠の青年団の皆さんが被災地に蕎麦を蒔いた。その蕎麦がまもなく実をつける。その蕎麦で、青年団は被災地で蕎麦を打って、被災地の皆さんに振る舞う。
その話を聞いて、やっぱり戸隠を続けようと、8月の戸隠に来ることを決めた。
まさかクーラーがないとは思ってもみなかった。
志の輔は来週から東北の被災地に行く。
被災地で避難所生活を余儀なくされている方がたを招待し、落語会を開く。
ある避難所では、一日の始めにリーダーが一本締めをするそうだ。
今日一日が希望をもって過ごせるように、避難所全員の心を一つにする「一本締め」。
その話を聞いて、志の輔は、独演会の最後に「一本締め」をするようになった。
「戸隠の皆さん、ガッテンしていただきましたでしょうか。」
大きな拍手の後、志の輔の音頭で、被災地が一日でも一時間でも早く、新しい生活を取り戻すことを祈って、
戸隠の夜に、一本締めが響いた。
第17回 志の輔 戸隠の夜
2011年8月5日(金)18時30分〜21時
・「親の顔が見たい」立川志の輔
・「お菊の皿」立川志の輔
2011年08月05日
夏草と石仏
天保の石仏の周辺には夏草が茂っている。

夏草だけでなく、まだ石仏の仲間たちがいる。

自在山へと誘う石の標識もある。
いまは線路に遮られているが、この辺りは自在山への参道であったのだろう。
自在山には神社がある。信仰の痕跡だ。

西国四国札所と刻まれた石標もある。
自在山の神社への参道の処どころには、西国と四国の札所の数だけ、石仏が置かれていたのかもしれない。
確かなことはわからない。

石仏には明らかに破壊の跡が見られるので、ある時点で石仏たちはその役目を終えたのだろう。
「廃仏毀釈」かもしれない。あるいはこの地を襲った水害の影響かもしれない。

信仰の対象を粗末にしない、地域の皆さんの思いがここには集まっていることは確かだ。

夏草だけでなく、まだ石仏の仲間たちがいる。
自在山へと誘う石の標識もある。
いまは線路に遮られているが、この辺りは自在山への参道であったのだろう。
自在山には神社がある。信仰の痕跡だ。
西国四国札所と刻まれた石標もある。
自在山の神社への参道の処どころには、西国と四国の札所の数だけ、石仏が置かれていたのかもしれない。
確かなことはわからない。
石仏には明らかに破壊の跡が見られるので、ある時点で石仏たちはその役目を終えたのだろう。
「廃仏毀釈」かもしれない。あるいはこの地を襲った水害の影響かもしれない。
信仰の対象を粗末にしない、地域の皆さんの思いがここには集まっていることは確かだ。
2011年08月04日
夕暮れ時に
まだ、夏本番を迎えていないのに、このごろ、秋を思うことが多い。


太平洋高気圧の張り出しが弱いのか、大陸の乾いた大気が流れ込んでいるのかはわからない。

ただ、夕暮れを迎える時間が早くなってきたことを感じる。

太平洋高気圧の張り出しが弱いのか、大陸の乾いた大気が流れ込んでいるのかはわからない。
ただ、夕暮れを迎える時間が早くなってきたことを感じる。
2011年08月03日
秋っぽい夏
血液型のせいにしてはいけないが、飽きっぽい僕はB型だ。
このところの空は秋っぽい。
要はこれが言いたかった前ふり。

通勤途上、赤トンボが前を横切り、つがいの黒トンボが飛び交い、黒揚羽が舞った。
それはそれで十分、感動的だが、シャッターが追従できない。
軒先の燕の子はだいぶ大きくなった。もう独り立ちできそうだ。


燕の子。君たちの季語は夏だよね。

このところの空は秋っぽい。
要はこれが言いたかった前ふり。
通勤途上、赤トンボが前を横切り、つがいの黒トンボが飛び交い、黒揚羽が舞った。
それはそれで十分、感動的だが、シャッターが追従できない。
軒先の燕の子はだいぶ大きくなった。もう独り立ちできそうだ。
燕の子。君たちの季語は夏だよね。
2011年08月02日
戌の満水、未曾有の大洪水。
小諸・佐久地方では、8月1日に一家で墓掃除をすると聞いた。
同僚に聞くと、母方の実家がある戸倉の対岸辺りの千曲川沿いにもその風習が残っていて、日曜日には墓掃除をしたという話だった。
長野に住み、戸倉で仕事をしている僕は、はじめて聞く風習だ。

この風習は、いまから270年近く遡る江戸時代に発生した大洪水、「戌の満水」に端を発している。
寛保2(1742)年7月末から降り続いた雨が止まず、8月 1 日(旧暦)には千曲川 の水位は通常の 10 倍近くに達し、堤防の決壊、土石流の発生が相次ぎ、千曲川流域だけで 2800 人を超える死者が出たという。小諸藩では浅間山からの土石流によって小諸城三の門が流され、犠牲者は584 人にのぼった。
小諸・佐久地方で、8月1日、お墓の掃除が行われるのは、その時に亡くなった方の霊を弔い、大洪水の悲劇を後世に伝え、備えを忘れるなという戒めである。会社や学校でも、午前中は休みになるところがあるそうだ。
「寛保二成年月未曾有の大洪水なり。七月二十九日より豪雨降続き、八月朔日夕より大暴風雨八月二日に至る。為に山抜け地滑り郡内到る所に及び、千曲川を始め諸支流皆狂奔怒号し、唯に沿岸の決壊浸水等に止まらす、河床を更ふるもの多く、上畑村の如き全部の流失、其他現時傳ふる所によるも南牧村、田口村、臼田町、切原村、大澤村、中込村等の惨状言語に絶するものあり。
人畜の死傷夥しく、平地浸水の民、居るに家なく、食するにものなく、皆飢餓に哭せりと伝う。後世呼んで戌年の大洪水と称す。」(南佐久郡誌より)

この戌の満水により、松代藩も大きな被害を受け、大規模な治水工事が行われ、幕府からの一万両に及ぶ借入金が、のちに松代藩の財政を逼迫させる。東北信一帯の、その後の社会、経済、風習文化に大きな影響を及ぼした大災害であった。
その年は、暖冬で冬から雨も多く、梅雨にも大量の降雨があった。梅雨前線と秋雨前線の活動がつながり、そのうえ、台風が前線を刺激し豪雨をもたらせたという。
季節外れの台風が発生し、前線を刺激している、今年の気象ともよく似ている。
8月1日、戌の満水。身近な歴史から学ぶべきことは、まだ多い。

同僚に聞くと、母方の実家がある戸倉の対岸辺りの千曲川沿いにもその風習が残っていて、日曜日には墓掃除をしたという話だった。
長野に住み、戸倉で仕事をしている僕は、はじめて聞く風習だ。
この風習は、いまから270年近く遡る江戸時代に発生した大洪水、「戌の満水」に端を発している。
寛保2(1742)年7月末から降り続いた雨が止まず、8月 1 日(旧暦)には千曲川 の水位は通常の 10 倍近くに達し、堤防の決壊、土石流の発生が相次ぎ、千曲川流域だけで 2800 人を超える死者が出たという。小諸藩では浅間山からの土石流によって小諸城三の門が流され、犠牲者は584 人にのぼった。
小諸・佐久地方で、8月1日、お墓の掃除が行われるのは、その時に亡くなった方の霊を弔い、大洪水の悲劇を後世に伝え、備えを忘れるなという戒めである。会社や学校でも、午前中は休みになるところがあるそうだ。
「寛保二成年月未曾有の大洪水なり。七月二十九日より豪雨降続き、八月朔日夕より大暴風雨八月二日に至る。為に山抜け地滑り郡内到る所に及び、千曲川を始め諸支流皆狂奔怒号し、唯に沿岸の決壊浸水等に止まらす、河床を更ふるもの多く、上畑村の如き全部の流失、其他現時傳ふる所によるも南牧村、田口村、臼田町、切原村、大澤村、中込村等の惨状言語に絶するものあり。
人畜の死傷夥しく、平地浸水の民、居るに家なく、食するにものなく、皆飢餓に哭せりと伝う。後世呼んで戌年の大洪水と称す。」(南佐久郡誌より)
この戌の満水により、松代藩も大きな被害を受け、大規模な治水工事が行われ、幕府からの一万両に及ぶ借入金が、のちに松代藩の財政を逼迫させる。東北信一帯の、その後の社会、経済、風習文化に大きな影響を及ぼした大災害であった。
その年は、暖冬で冬から雨も多く、梅雨にも大量の降雨があった。梅雨前線と秋雨前線の活動がつながり、そのうえ、台風が前線を刺激し豪雨をもたらせたという。
季節外れの台風が発生し、前線を刺激している、今年の気象ともよく似ている。
8月1日、戌の満水。身近な歴史から学ぶべきことは、まだ多い。
2011年07月31日
プレイバック、文月。
早々と梅雨が明けたかと思いきや、夕方近くになると激しい雷雨が襲い、まだ梅雨かなと思わせる空が広がる。
大気の安定しない七月だった。
北京でも同じような気候のようで、東アジアの空が連続していることを知る。

雷光をキャッチするには瞬発力より忍耐力が必要。

ワイナリーは暑さを避けて佇むには、ちょうど佳い。


七月の日照と雨は、今年の葡萄にどう影響するのだろう。
ブクオで「ワイン」という古本を買った。著者はなだいなだ。
ワインという題名なのに、ワインという言葉を一度しか使っていない。ほかはすべて「ブドー酒」。
ワインとブドー酒の違いは、ライスとごはんの違い。1974年初版の平凡社カラー新書。

この天候のお陰で、家庭菜園の野菜たちは元気である。
夜半の雨が胡瓜には良かった。茄子、トマトも昨年よりよい感じ。


バジルとイタリアンパセリはうまく馴染んでくれた。

通い始めた古代史講座は、夏休みの補習を思い出す。


古代の史料の残り方は在野でも研究可能な領域だし、考古史料の新発見があれば、定説も覆るという痛快さもある。
屋代遺跡群の7世紀木簡を解析しながら古代の地方社会の実像に迫る講義は、知的好奇心の満足度大。

学習院大学文学部史学科教授 鐘江宏之先生


時間が経つにつれて、興が乗ってくる感じの講師のパフォーマンスも良かった。ここにもプロフェッショナルあり。

蝉の鳴かない夏ですね。というつぶやきも多かった。
「寒蝉鳴」ひぐらしが鳴き始めること。
ホームのベンチに腰掛けて、ひぐらしの声を山から聞きながら、読みかけの文庫本をひろげて帰りの列車を待つ。
立秋は八月八日。


大気の安定しない七月だった。
北京でも同じような気候のようで、東アジアの空が連続していることを知る。
雷光をキャッチするには瞬発力より忍耐力が必要。
ワイナリーは暑さを避けて佇むには、ちょうど佳い。
七月の日照と雨は、今年の葡萄にどう影響するのだろう。
ブクオで「ワイン」という古本を買った。著者はなだいなだ。
ワインという題名なのに、ワインという言葉を一度しか使っていない。ほかはすべて「ブドー酒」。
ワインとブドー酒の違いは、ライスとごはんの違い。1974年初版の平凡社カラー新書。
この天候のお陰で、家庭菜園の野菜たちは元気である。
夜半の雨が胡瓜には良かった。茄子、トマトも昨年よりよい感じ。
バジルとイタリアンパセリはうまく馴染んでくれた。
通い始めた古代史講座は、夏休みの補習を思い出す。
古代の史料の残り方は在野でも研究可能な領域だし、考古史料の新発見があれば、定説も覆るという痛快さもある。
屋代遺跡群の7世紀木簡を解析しながら古代の地方社会の実像に迫る講義は、知的好奇心の満足度大。
学習院大学文学部史学科教授 鐘江宏之先生
時間が経つにつれて、興が乗ってくる感じの講師のパフォーマンスも良かった。ここにもプロフェッショナルあり。
蝉の鳴かない夏ですね。というつぶやきも多かった。
「寒蝉鳴」ひぐらしが鳴き始めること。
ホームのベンチに腰掛けて、ひぐらしの声を山から聞きながら、読みかけの文庫本をひろげて帰りの列車を待つ。
立秋は八月八日。
2011年07月21日
2011年07月11日
突然の雷雨、そして停電
そろそろ帰ろうかという時間になり、空に雲が覆い、激しい夕立があった。
轟く雷鳴。パソコンも瞬間停電。
しなの鉄道は、停電により運行停止、ダイヤに大幅な乱れという情報をチャッチしているうちに、姨捨方面に夕陽。

雨は激しいままやむことなく、夕陽はその雨の中を姨捨山へと沈んでいく。

しなの鉄道が動くまではと、会社の最上階で沈む夕陽を眺めることにした。
上田方面には、虹がかかった。

冠着山の山頂付近には、白い雲が湧き、高い雲は茜色に染まる。

戸倉の上空は、白馬からの大気が激しく流れ込む場所だ。

不安定な大気がこの上空で、その不安定さゆえに変幻万化する気流となって、軌跡を遺す。
気流の流れる音が聞こえたような気がした。
大気が澄んで、空が近くに迫り、雲の渦の中に巻き込まれるような感覚に陥った。


茜色の空に闇の気配が迫ると、遠くから列車が走る音が聞こえてきた。
しなの鉄道、運行再開。

轟く雷鳴。パソコンも瞬間停電。
しなの鉄道は、停電により運行停止、ダイヤに大幅な乱れという情報をチャッチしているうちに、姨捨方面に夕陽。
雨は激しいままやむことなく、夕陽はその雨の中を姨捨山へと沈んでいく。
しなの鉄道が動くまではと、会社の最上階で沈む夕陽を眺めることにした。
上田方面には、虹がかかった。
冠着山の山頂付近には、白い雲が湧き、高い雲は茜色に染まる。
戸倉の上空は、白馬からの大気が激しく流れ込む場所だ。
不安定な大気がこの上空で、その不安定さゆえに変幻万化する気流となって、軌跡を遺す。
気流の流れる音が聞こえたような気がした。
大気が澄んで、空が近くに迫り、雲の渦の中に巻き込まれるような感覚に陥った。
茜色の空に闇の気配が迫ると、遠くから列車が走る音が聞こえてきた。
しなの鉄道、運行再開。
2011年07月11日
涼しさと静けさ、戸隠奥社
七曲がりから飯綱に登り、戸隠奥社入り口まで30分余り。
暑さから遁げ出す先は、戸隠の霊場。

杉木立に陽は遮られ、鳥の啼く声が静寂のなかに谺すだけ。


でも、少し出遅れたかな。

今日のところは「随神門」までにしておきます。
戸隠には、十分に陽が昇る前に訪ねることにしよう。

参道の道すがら、ここにも涼と静がある。



暑さから遁げ出す先は、戸隠の霊場。
杉木立に陽は遮られ、鳥の啼く声が静寂のなかに谺すだけ。
でも、少し出遅れたかな。
今日のところは「随神門」までにしておきます。
戸隠には、十分に陽が昇る前に訪ねることにしよう。
参道の道すがら、ここにも涼と静がある。
2011年07月09日
空と雲の輝き、そして稲妻
いよいよ、夏本番の入道雲、ぐんぐん垂直に伸びていく。
猛烈に暑い夏が帰ってきた。

これは昨夕の梅雨明けのサイン。

明けましたね、おめでとう。

空と雲のあいだに虹が輝く。ほんの瞬間



入道雲がくずれ、黒雲が広がる。


そして、激しい雨。
稲妻。

変幻する空と雲。
たかだか2時間弱、一瞬の夏の幕開け。
猛烈に暑い夏が帰ってきた。
これは昨夕の梅雨明けのサイン。
明けましたね、おめでとう。
空と雲のあいだに虹が輝く。ほんの瞬間
入道雲がくずれ、黒雲が広がる。
そして、激しい雨。
稲妻。
変幻する空と雲。
たかだか2時間弱、一瞬の夏の幕開け。
2011年07月06日
2011年07月05日
ワイン葡萄の栽培管理
この時期のぶどうは生長が早い。前回のセミナーから一ヶ月経った岩の原葡萄園。
レインカットが張られ、実習圃場が様相を変えている。
レインカットはぶどう棚全体を覆うビニールの傘だ。梅雨どきの高温多湿は、葡萄の大敵「ベト病」を発生させるので、この傘でそれを防ぐ。
ビフォー 2011年5月28日
アフター 2011年7月2日
ぶどうの四季セミナーの今回のテーマは「防除(ぼうじょ)」について。防除とは、病虫害から葡萄を守る取組みのこと。レインカットもその一つ。
講師の先生は、朝5時からSS(スピードスプレイヤー)でボルドー液の散布を終えたばかりで、疲労の色が見える。SSで30往復し、葡萄園全体にボルドー液を散布したそうだ。
恐れていたベト病が発生したらしい。本当はセミナーどころではない非常事態。
葡萄園ではベト病に細心の注意を払う。ベト病にやられると、葉には淡黄色の輪郭の不明瞭な斑点が現れ、斑点の裏面には白色のかびが生える。ベト病が発生したら、菌が散らないように発生した箇所を除去して、圃場から完全に撤去する。
ボルドー液を散布するがあくまでも予防であり、病気そのものには効かない。
ボルドー液:硫酸銅と生石灰を混合して作る殺菌剤。 施用すると作物体表面に薄い皮膜ができ、外部からの病原菌の侵入を防ぐ。また、銅 イオンが発生して殺菌作用を示す。
「有機農産物の日本農林規格」において、有機農産物への使用が禁止されていない。
こちらは鳥の害からの防除網。
カラスと椋鳥は葡萄が好物。人間が旨いものは鳥にもわかるらしい。
これだけの労力と時間をかけて、ワイン葡萄の防除を行うのは、ひとえに「良いワインは良い葡萄から」という信念に基づいているからだ。
良い葡萄を収穫するためには「管理」が必要だ。ここがビジネスと趣味との境界線だ。
栽培管理の立場からよいワイン葡萄とは、まずは「凝縮感」があること。
・粒はあまり大きくなく、房も大き過ぎず。葡萄の粒は小さいほど果汁に対する果皮の比率が高まり、果皮からの抽出される成分で着色や凝縮感が高まる。
・アルコール度数14%のワインを造るには、24%程度の糖度が必要である。生食用の葡萄14~18%が主流。
・糖度は高いほどよいが、適度な酸味も必要で、完熟度が高いと酸味が少なく、切れがなくなる。完熟度が低いと酸味が強く、ワインに切れが出る。
そして、「収量制限」。収量は一定以上を超えてはいけない。収量が増えるとワインの品質に悪い影響が出る。
・収穫量のコントロールには、剪定時期から芽数制御や仕立検討などの収量設計を行う。
・岩の原では、10アールの圃場に対して、葡萄の収穫量は10トン。およそ、ワイン1万本に相当する。
・ロマネコンティは、ワイン法により10アールに対して500キログラム以下と定められている。
芽が出てから以降は、設計を超える新芽・新梢は摘み取り、房の重量もコントロールする。
・岩の原では、一本の枝に一房が原則。葉の数は一枝あたり12~13枚。房の重量は500グラム。
病害虫による収量の減少を防ぐための取組みが防除。さまざまな手法を取り混ぜて、葡萄を守る。
ここまで手間をかけて、条件に合致した品質の葡萄を栽培する。
品質管理の行き届いた葡萄は、良質のワイン醸造を約束してくれる。
どこか、これは日本の製造業に共通するところがある。
「品質は工程で造り込め」。
良いワインは葡萄栽培の工程で造り込まれる。
2011年07月04日
ホームラン亭流
須坂に行くと、立ち寄ってしまうのがホームラン亭。

須坂ショッピングセンターとして、華々しくオープンした時、ここを訪れた小学生の記憶がある。
あの頃は須坂の街も元気だった。いまはシャッターを閉じてしまった店が多い。
この商店街に漂う昭和の原点が、ここホームラン亭だ。
お気に入りは「ワンタンメン」。

いつか隣に座った常連さんと思しき人の食べ方を、ここの流儀として踏襲している。
ホームラン亭の流儀
その一、すり胡麻をかける。

その二、酢をかける。

この二つ、だけ。
胡麻は胡麻すり器でする。ゴマをするのは馴れたもんである。

こってりとした豚骨のスープは、酢によって、濃厚さがほどよく抑えられる。
疲れているときには、最後の一滴まで、豚骨スープを飲み干す。
酢は身体にいいんだと信じてる。
営業時間は限られている。営業してればラッキーだが、行列かもしれない。


須坂商店街パルム街を抜けると、旧い町の再生が始まっている。
須坂ショッピングセンターとして、華々しくオープンした時、ここを訪れた小学生の記憶がある。
あの頃は須坂の街も元気だった。いまはシャッターを閉じてしまった店が多い。
この商店街に漂う昭和の原点が、ここホームラン亭だ。
お気に入りは「ワンタンメン」。
いつか隣に座った常連さんと思しき人の食べ方を、ここの流儀として踏襲している。
ホームラン亭の流儀
その一、すり胡麻をかける。
その二、酢をかける。
この二つ、だけ。
胡麻は胡麻すり器でする。ゴマをするのは馴れたもんである。
こってりとした豚骨のスープは、酢によって、濃厚さがほどよく抑えられる。
疲れているときには、最後の一滴まで、豚骨スープを飲み干す。
酢は身体にいいんだと信じてる。
営業時間は限られている。営業してればラッキーだが、行列かもしれない。
須坂商店街パルム街を抜けると、旧い町の再生が始まっている。
2011年07月03日
懐かしい涼しさ
須坂のホームラン亭でワンタンメンを食べて、通りに出るとよい香りが漂ってきた。店先で香を焚いている。
そして、なんともレトロな扇風機で涼を取っているお店があった。

旧い町家を改造し、天井をはらった広々とした吹き抜け空間が魅力的だ。

革の鞄や小物入れ、アクセサリーや、自然の素材感を大切にした服を取り扱っている。

町家を再生して、新しい空間を楽しんでいるオーナーの姿勢が、並んでいる品物のセンスになって光る。

「BLLAD OF THE SUN」。旧い町に新しい陽射し。

ここで手に入れたものは、ずっと大切にしていけそうな気がする。

須坂市は旧谷街道、蔵の街です。


そして、なんともレトロな扇風機で涼を取っているお店があった。
旧い町家を改造し、天井をはらった広々とした吹き抜け空間が魅力的だ。
革の鞄や小物入れ、アクセサリーや、自然の素材感を大切にした服を取り扱っている。
町家を再生して、新しい空間を楽しんでいるオーナーの姿勢が、並んでいる品物のセンスになって光る。
「BLLAD OF THE SUN」。旧い町に新しい陽射し。
ここで手に入れたものは、ずっと大切にしていけそうな気がする。
須坂市は旧谷街道、蔵の街です。
2011年07月02日
七二会の日、三三
七月二日は、なんの日か、ご存知ですか。
「何」の日ではなくで、この日は「七二会の日」。長野市七二会(なにあい)、頑張ってる東京電力小田切ダムから犀川に沿った里山に広がる地域である。
この七二会の商工会のメンバーが始めたのが、七月二日に開催する「七二会寄席」。今年で9回目。

この七二会寄席に8回連続で出演しているのが、柳家三三師匠。いまや若手真打ちの中でも実力と人気が伴った超売れっ子の一人である。
8回連続ということは、二つ目時代からで続けていることになる。そして、売れっ子となったいまでも忙しいスケジュールの合間をぬって、七二会寄席に出てくれている。そこんところの人情に惹かれるね。


七二会寄席は、開催日だけでなく、「七」と「二」にこだわっている。今年は七二歳になるお年寄りを14名無料招待したそうだ。
商工会の皆さんが、受付や会場係、駐車場係とこの落語会を支えている。参加者のみなさんも、面白かった、また来るねと、スタッフに気さくに声をかけていく。
アットホームな雰囲気が、三三師の連続出演のエネルギーになっているかもしれない。

第9回七二会寄席
長野市・七二会商工会館
・「看板のピン」柳家三三
・ギター漫談 鈴々舎馬るこ
・「鮑のし」柳家三三
「何」の日ではなくで、この日は「七二会の日」。長野市七二会(なにあい)、頑張ってる東京電力小田切ダムから犀川に沿った里山に広がる地域である。
この七二会の商工会のメンバーが始めたのが、七月二日に開催する「七二会寄席」。今年で9回目。
この七二会寄席に8回連続で出演しているのが、柳家三三師匠。いまや若手真打ちの中でも実力と人気が伴った超売れっ子の一人である。
8回連続ということは、二つ目時代からで続けていることになる。そして、売れっ子となったいまでも忙しいスケジュールの合間をぬって、七二会寄席に出てくれている。そこんところの人情に惹かれるね。
七二会寄席は、開催日だけでなく、「七」と「二」にこだわっている。今年は七二歳になるお年寄りを14名無料招待したそうだ。
商工会の皆さんが、受付や会場係、駐車場係とこの落語会を支えている。参加者のみなさんも、面白かった、また来るねと、スタッフに気さくに声をかけていく。
アットホームな雰囲気が、三三師の連続出演のエネルギーになっているかもしれない。
第9回七二会寄席
長野市・七二会商工会館
・「看板のピン」柳家三三
・ギター漫談 鈴々舎馬るこ
・「鮑のし」柳家三三