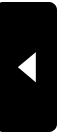2011年07月01日
プレイバック、水無月
水の無い月と書くが水が無いわけでない。
水無月の「無」は、「の」にあたる連体助詞「な」で、「水のつき」という意味である。
陰暦六月が田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。(©語源由来辞典)
上山田善光寺別院の睡蓮

書道ガールズの墨跡

deco cafe のハーブ

インディア・ザ・ロックのネオン

住宅街のサンクチュアリー

一瞬の梅雨明け



陰暦七月は稲穂が膨らむ月であるため「穂含月(ほふみつき)」から転じて、文月となる。(©語源由来辞典)
水無月の「無」は、「の」にあたる連体助詞「な」で、「水のつき」という意味である。
陰暦六月が田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。(©語源由来辞典)
上山田善光寺別院の睡蓮
書道ガールズの墨跡
deco cafe のハーブ
インディア・ザ・ロックのネオン
住宅街のサンクチュアリー
一瞬の梅雨明け
陰暦七月は稲穂が膨らむ月であるため「穂含月(ほふみつき)」から転じて、文月となる。(©語源由来辞典)
2011年06月30日
ねぐらに還る、鳥の群れ
夕暮れ時になると、長野市中からねぐらに還ってくる鳥たち。
さながらヒッチコックは「鳥」の光景だ。


近所で、鳥たちのねぐらになっているのがこのポプラ並木だ。
このポプラ並木の北側は、貯水池になっていて、鳥たちのサンクチュアリー。



鳥たちの住所ですか。お教えしないことになっているんですがね。

(こっそりと、お教えします)長野市の三重公園の近くです。
ここは住宅地のど真ん中にある鳥たちの楽園であり、ねぐらである。

そおっとしておいてくださいね。
さながらヒッチコックは「鳥」の光景だ。
近所で、鳥たちのねぐらになっているのがこのポプラ並木だ。
このポプラ並木の北側は、貯水池になっていて、鳥たちのサンクチュアリー。
鳥たちの住所ですか。お教えしないことになっているんですがね。
(こっそりと、お教えします)長野市の三重公園の近くです。
ここは住宅地のど真ん中にある鳥たちの楽園であり、ねぐらである。
そおっとしておいてくださいね。
2011年06月29日
夕景、梅雨は明けたかな
長野駅に着くと入道雲がお出迎え。
梅雨が明けたかのような空。
大気が流れて、雲の形がじっとしていない。風は冷たい。

しなの鉄道の車窓から見えたメタリックな雲。

犀川を渡る鉄橋。夕陽はまだ、沈まない。

澄み渡った空に雲ふたつ、二題。


巣に帰る鷺、家に帰る僕。

ふたたび、ここは南フランス、結婚式の街ですか。

梅雨が明けたかのような空。
大気が流れて、雲の形がじっとしていない。風は冷たい。
しなの鉄道の車窓から見えたメタリックな雲。
犀川を渡る鉄橋。夕陽はまだ、沈まない。
澄み渡った空に雲ふたつ、二題。
巣に帰る鷺、家に帰る僕。
ふたたび、ここは南フランス、結婚式の街ですか。
2011年06月29日
萱のあじさい
夜半に雨が降り、未明には上がるという好循環な梅雨である。
戸倉駅に向かう交差点にある苔むした萱葺き屋根。戸倉宿で400年の歴史をもつ酒蔵であり、蕎麦料理処「萱」。
白壁の片隅にあじさいが咲いていた。これほど、雨の似合う花はないが、でんでん虫のかわりにカナブンがいた。

色とりどり、紫陽花ではなく、あじさいの気分。



苔むす萱葺き屋根。

軒下には燕の巣。

つばくろや酒蔵すみの萱あじさい

戸倉駅に向かう交差点にある苔むした萱葺き屋根。戸倉宿で400年の歴史をもつ酒蔵であり、蕎麦料理処「萱」。
白壁の片隅にあじさいが咲いていた。これほど、雨の似合う花はないが、でんでん虫のかわりにカナブンがいた。
色とりどり、紫陽花ではなく、あじさいの気分。
苔むす萱葺き屋根。
軒下には燕の巣。
つばくろや酒蔵すみの萱あじさい
2011年06月28日
ラスト前の平治
初回は「らくだ」、二回めが「源平盛衰記」、そして今回は新作の「幽霊の辻」。
来年9月下席より、十一代目桂文治を襲名することになった桂平治を迎えての寿限無寄席は「新緑の笑」。

前日は、松本のアルプス寄席。ホテル屋上階の大浴場でのんびり過ごした平治師。ホテルのチェックアウトしたのが午後1時。2時半の高速バスに乗って、車窓より姨捨山の眺望を楽しみ、川中島の古戦場を通り過ぎて、長野駅に到着したのが、4時。約束時間までの30分でずんだミルクコーヒー。これがあまり旨くなかったようで。
さあて。満を持しての高座は、たっぷり二席。

全身を使い、顔の筋肉を総動員して、演じたのが「肥かめ」。
身体の使い方、視線の送り方が、権太楼に似ている。似ているというのは失礼かもしれない。物真似できない奴は駄目だと言ったのは談志。落語は、師匠からの相伝である。師匠を亡くした平治のいまの師匠は権太楼なのだろうか。
二席めは、新作落語の「幽霊の辻」。大阪市生まれの落語作家・小佐田定雄の新作落語。 上方の桂枝雀が演じたが、いまは権太楼がよく演る噺である。なるほど、平治は権太楼と格闘しているのか。

源平盛衰記は、師匠の十代目文治譲り。そして、十一代目を襲名するにあたり、権太楼を真似ながら自分の中で平治自身を壊している。思えば、一番始めに聴いた「らくだ」は平治そのものだった。先代師匠をなぞり、爆笑系の第一人者を模倣し、それぞれを平治のものにしながら、その先にある十一代目文治を創造していく姿。これが大名跡を継ぐ者だけが知る重責。平治を否定する向こうに拓ける十一代目の地平。

大看板になるともうお呼びできないかもと、居酒屋寿限無の女将。
また、平治のうちに来ますという、平治師匠。
十一代目文治へとメタモルフォーゼしていくラスト前、さなぎから蝶へ孵化する寸前の平治を観たい。
第28回 寿限無寄席
居酒屋寿限無2階の座敷
・「肥かめ」 桂平治
・「幽霊の辻」 桂平治

来年9月下席より、十一代目桂文治を襲名することになった桂平治を迎えての寿限無寄席は「新緑の笑」。
前日は、松本のアルプス寄席。ホテル屋上階の大浴場でのんびり過ごした平治師。ホテルのチェックアウトしたのが午後1時。2時半の高速バスに乗って、車窓より姨捨山の眺望を楽しみ、川中島の古戦場を通り過ぎて、長野駅に到着したのが、4時。約束時間までの30分でずんだミルクコーヒー。これがあまり旨くなかったようで。
さあて。満を持しての高座は、たっぷり二席。
全身を使い、顔の筋肉を総動員して、演じたのが「肥かめ」。
身体の使い方、視線の送り方が、権太楼に似ている。似ているというのは失礼かもしれない。物真似できない奴は駄目だと言ったのは談志。落語は、師匠からの相伝である。師匠を亡くした平治のいまの師匠は権太楼なのだろうか。
二席めは、新作落語の「幽霊の辻」。大阪市生まれの落語作家・小佐田定雄の新作落語。 上方の桂枝雀が演じたが、いまは権太楼がよく演る噺である。なるほど、平治は権太楼と格闘しているのか。
源平盛衰記は、師匠の十代目文治譲り。そして、十一代目を襲名するにあたり、権太楼を真似ながら自分の中で平治自身を壊している。思えば、一番始めに聴いた「らくだ」は平治そのものだった。先代師匠をなぞり、爆笑系の第一人者を模倣し、それぞれを平治のものにしながら、その先にある十一代目文治を創造していく姿。これが大名跡を継ぐ者だけが知る重責。平治を否定する向こうに拓ける十一代目の地平。
大看板になるともうお呼びできないかもと、居酒屋寿限無の女将。
また、平治のうちに来ますという、平治師匠。
十一代目文治へとメタモルフォーゼしていくラスト前、さなぎから蝶へ孵化する寸前の平治を観たい。
第28回 寿限無寄席
居酒屋寿限無2階の座敷
・「肥かめ」 桂平治
・「幽霊の辻」 桂平治
2011年06月27日
想いは若いままで
徳田建さんとまじさんが長野に戻ってきてくれた。
高校の同窓会があったので、同窓生を誘い、下山さんのライブで偶然出遭った同級生も来てくれた。

徳田建さんは、まじさんと一緒になってから3回目の長野。「新緑の信州もいいですよ」とお奨めしてからこの時期に来てくれるようになった。
10人も入ればいっぱいとなるライブハウスだけれど、だからこそ、ステージと客席が一体となった濃密な空間が広がり、贅沢な時間が流れていく。いつもありがたいと思いながら、もったいないと感じている。ふたりのライブを、少しでも多くの長野の皆さんに聴いてほしいなと、回を重ねるごとにその気持ちは募っていく。

ヒア・カム・ザ・サン Here Comes The Sun で、幕開き。
さらに優しくなった徳田建さんの歌声。
NHK-BS出演以来、テクニックに磨きがかかったまじさんのスティール・ギターの「泣き」がからんでいく。
ボブ・ディランのフォエバー・ヤング Forever Young
僕にとっての、思い出の曲。マイ・バック・ページズ My Back Pages
徳田建さんの訳詞がしっくり心にはまる。

激しさもまじさんの表現のひとつ。まじさんって、闘ってるんだと感じるギターソロ。
まじさんの「今日は休むと決めたんだ♪」で、全員が明日はぜったい休むことを宣言する。
高田渡の「夕暮れ」。
詩は黒田三郎。僕が持っていた数少ない詩集のひとつは、黒田三郎だった。
この歌には、自分の姿が重なって見えるときがある。

夕暮れの町で
僕は見る
自分の場所からはみ出してしまった
多くのひとびとを
夕暮れのビヤホールで
ひとり
一杯のジョッキをまえに
斜めに座る
その目が
この世の誰とも交わらないところを
えらぶ
そうやってたかだか三十分か一時間

そして、徳田建さんが長野に来ると歌うという田中研二の「すすき川の流れる所」。
学生時代を松本で過ごした同級生が、この歌で感慨に耽っていた。
若い日の情景が浮かんできたそうだ。そう、よかった。この曲が聴けただけでも、なかば強引に連れてきた甲斐があったというもの。
最後は、建さんのオリジナル曲「犬の唄」、アンコールに応えて「ハッピードッグ」
Happy man with good dog happy dog with good man
Happy man with good dog happy dog with good man
僕ら同級生は戌(いぬ)年でした。まじさんも。
最初に「優しい世代」と言われたのも僕たちです。

僕らがその背中を見ながら追いかけてきた世代の徳田建さん、まじさんは同世代で、僕らが諦めたり失った夢を手にしながら音楽表現を続けている。
ふたりの音楽に身をゆだねると、時代のなかに埋めてきた想いが若いままの貌で甦ってくる。
郷愁ではなく、失った夢を一つひとつ取り戻していくことを始めた「大人」が、その夢を若さという形で取り戻す瞬間がこのライブにはある。

高校の同窓会があったので、同窓生を誘い、下山さんのライブで偶然出遭った同級生も来てくれた。
徳田建さんは、まじさんと一緒になってから3回目の長野。「新緑の信州もいいですよ」とお奨めしてからこの時期に来てくれるようになった。
10人も入ればいっぱいとなるライブハウスだけれど、だからこそ、ステージと客席が一体となった濃密な空間が広がり、贅沢な時間が流れていく。いつもありがたいと思いながら、もったいないと感じている。ふたりのライブを、少しでも多くの長野の皆さんに聴いてほしいなと、回を重ねるごとにその気持ちは募っていく。
ヒア・カム・ザ・サン Here Comes The Sun で、幕開き。
さらに優しくなった徳田建さんの歌声。
NHK-BS出演以来、テクニックに磨きがかかったまじさんのスティール・ギターの「泣き」がからんでいく。
ボブ・ディランのフォエバー・ヤング Forever Young
僕にとっての、思い出の曲。マイ・バック・ページズ My Back Pages
徳田建さんの訳詞がしっくり心にはまる。
激しさもまじさんの表現のひとつ。まじさんって、闘ってるんだと感じるギターソロ。
まじさんの「今日は休むと決めたんだ♪」で、全員が明日はぜったい休むことを宣言する。
高田渡の「夕暮れ」。
詩は黒田三郎。僕が持っていた数少ない詩集のひとつは、黒田三郎だった。
この歌には、自分の姿が重なって見えるときがある。
夕暮れの町で
僕は見る
自分の場所からはみ出してしまった
多くのひとびとを
夕暮れのビヤホールで
ひとり
一杯のジョッキをまえに
斜めに座る
その目が
この世の誰とも交わらないところを
えらぶ
そうやってたかだか三十分か一時間
そして、徳田建さんが長野に来ると歌うという田中研二の「すすき川の流れる所」。
学生時代を松本で過ごした同級生が、この歌で感慨に耽っていた。
若い日の情景が浮かんできたそうだ。そう、よかった。この曲が聴けただけでも、なかば強引に連れてきた甲斐があったというもの。
最後は、建さんのオリジナル曲「犬の唄」、アンコールに応えて「ハッピードッグ」
Happy man with good dog happy dog with good man
Happy man with good dog happy dog with good man
僕ら同級生は戌(いぬ)年でした。まじさんも。
最初に「優しい世代」と言われたのも僕たちです。
僕らがその背中を見ながら追いかけてきた世代の徳田建さん、まじさんは同世代で、僕らが諦めたり失った夢を手にしながら音楽表現を続けている。
ふたりの音楽に身をゆだねると、時代のなかに埋めてきた想いが若いままの貌で甦ってくる。
郷愁ではなく、失った夢を一つひとつ取り戻していくことを始めた「大人」が、その夢を若さという形で取り戻す瞬間がこのライブにはある。
2011年06月24日
二番目に昼が長い日
6月22日は「夏至」だった。そう、一年で一番、昼の長い日である。
では、二番目に昼が長いのは、夏至の前日なのか、翌日なのか。夏至を頂点とすると、これから下り坂の翌日が短いような気もするし、でもこれから夏本番だし、翌日のが長いかなと考えたり。
前日と翌日は同じだろうと常識人の自分がしたり顔をする。

国立天文台には、暦計算室とセクションがあり、都道府県庁所在地等の日の出・日の入り、月の出・月の入り、南中時を「各地のこよみ」として、まとめている。
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/
さすが、国立天文台ですね。
ありましたよ。
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
ムムッ。標高ゼロメートル。
注意書きを見て納得。「出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。」理論値なんですね。
日の出の時刻と日の入りの時刻から、昼間の時間を計算して、まとめてみたのがこの表です。

栄えある「一年で二番目に昼間の長い日」は、
夏至の前日である、6月21日でした。
そして、サプライズ。
一年で一番、昼間の長い日は、夏至の翌日である、
6月23日ではありませんか。そして、6月24日、夏至の前の6月19日も、14時間41分。
夏至の6月22日は、14時間40分で、前日と同じで、2番目の日でした。
これは、ここ長野だけの話でしょうか。各地のこよみを検証する「ずく」はなし。暑くて

6月22日は、「夏至日」といい、日の出・日の入りの方角が最も北寄りになる日をいうそうです。
「昼が最も長い夏至の今日」という言い回しを何度も耳にしたけれど、必ずも「夏至の日」の昼の時間が一年中で最も長いわけではないようです。
7月31日までは連日14時間を超える昼間が続き、8月中は、昼間の時間は13時間台です。9月になると、昼間の時間は13時間を切り、9月27日には昼と夜との長さが同じになります。
ちなみに、今年の秋分の日は9月23日です。

夏至(Wikipedia フリー百科事典より)
春分から秋分までの間、北半球では太陽は真東からやや北寄りの方角から上り、真西からやや北寄りの方角に沈む。
夏至の日にはこの日の出(日出)・日の入り(日没)の方角が最も北寄りになる。
また、北回帰線上の観測者から見ると、夏至の日の太陽は正午に天頂を通過する。
夏至の日には北緯66.6度以北の北極圏全域で白夜となり、南緯66.6度以南の南極圏全域で極夜となる。
なお、1年で日の出の時刻が最も早い日・日の入りの時刻が最も遅い日と、夏至の日とは一致しない。日本では、日の出が最も早い日は夏至の1週間前ごろであり、日の入りが最も遅い日は夏至の1週間後ごろである。
では、二番目に昼が長いのは、夏至の前日なのか、翌日なのか。夏至を頂点とすると、これから下り坂の翌日が短いような気もするし、でもこれから夏本番だし、翌日のが長いかなと考えたり。
前日と翌日は同じだろうと常識人の自分がしたり顔をする。

国立天文台には、暦計算室とセクションがあり、都道府県庁所在地等の日の出・日の入り、月の出・月の入り、南中時を「各地のこよみ」として、まとめている。
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/
さすが、国立天文台ですね。
ありましたよ。
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
ムムッ。標高ゼロメートル。
注意書きを見て納得。「出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。」理論値なんですね。
日の出の時刻と日の入りの時刻から、昼間の時間を計算して、まとめてみたのがこの表です。
栄えある「一年で二番目に昼間の長い日」は、
夏至の前日である、6月21日でした。
そして、サプライズ。
一年で一番、昼間の長い日は、夏至の翌日である、
6月23日ではありませんか。そして、6月24日、夏至の前の6月19日も、14時間41分。
夏至の6月22日は、14時間40分で、前日と同じで、2番目の日でした。
これは、ここ長野だけの話でしょうか。各地のこよみを検証する「ずく」はなし。暑くて

6月22日は、「夏至日」といい、日の出・日の入りの方角が最も北寄りになる日をいうそうです。
「昼が最も長い夏至の今日」という言い回しを何度も耳にしたけれど、必ずも「夏至の日」の昼の時間が一年中で最も長いわけではないようです。
7月31日までは連日14時間を超える昼間が続き、8月中は、昼間の時間は13時間台です。9月になると、昼間の時間は13時間を切り、9月27日には昼と夜との長さが同じになります。
ちなみに、今年の秋分の日は9月23日です。

夏至(Wikipedia フリー百科事典より)
春分から秋分までの間、北半球では太陽は真東からやや北寄りの方角から上り、真西からやや北寄りの方角に沈む。
夏至の日にはこの日の出(日出)・日の入り(日没)の方角が最も北寄りになる。
また、北回帰線上の観測者から見ると、夏至の日の太陽は正午に天頂を通過する。
夏至の日には北緯66.6度以北の北極圏全域で白夜となり、南緯66.6度以南の南極圏全域で極夜となる。
なお、1年で日の出の時刻が最も早い日・日の入りの時刻が最も遅い日と、夏至の日とは一致しない。日本では、日の出が最も早い日は夏至の1週間前ごろであり、日の入りが最も遅い日は夏至の1週間後ごろである。
2011年06月23日
はぜかけ米のおにぎり
しなの鉄道の戸倉駅の待合室は、信州有機倶楽部の農産物直売所であったり、喫茶店があったり、日本版ファストフードである立食いそば屋「かかし」であったりする。
かかしには、姨捨山は棚田のはぜかけ米で握ったおにぎりがある。これが旨い。

はぜに稲穂をかけて、自然の力でゆっくり乾燥させた米が「はぜかけ米」。時間をかけてじっくりと乾燥するため、熟成が進み、旨味が凝縮した米だ。
おにぎりをほお張ると米のうまさがダイレクト伝わってくる。これが米の味なんだと実感できる。おにぎりは、焼きたらこ、ねぎ味噌、焼き鮭が米の味を損ねない程度にトッピングされている。お気に入りは、醤油味の焼きおにぎり、香ばしさとはぜかけ米の味のバランスがなんとも絶妙である。

信州有機倶楽部の直売所は、キャベツやズッキーニなど季節の野菜が手ごろな価格で並んでいる。夏も盛りになると、ラクビーボールの形をした西瓜も並ぶはずだ。


いまのおすすめは烏骨鶏の卵と古代米。烏骨鶏の卵は1パック4個入りで480円。これが高いのか安いのかはわからない。

待ち時間も楽しい、しなの鉄道は戸倉駅。
かかしには、姨捨山は棚田のはぜかけ米で握ったおにぎりがある。これが旨い。
はぜに稲穂をかけて、自然の力でゆっくり乾燥させた米が「はぜかけ米」。時間をかけてじっくりと乾燥するため、熟成が進み、旨味が凝縮した米だ。
おにぎりをほお張ると米のうまさがダイレクト伝わってくる。これが米の味なんだと実感できる。おにぎりは、焼きたらこ、ねぎ味噌、焼き鮭が米の味を損ねない程度にトッピングされている。お気に入りは、醤油味の焼きおにぎり、香ばしさとはぜかけ米の味のバランスがなんとも絶妙である。
信州有機倶楽部の直売所は、キャベツやズッキーニなど季節の野菜が手ごろな価格で並んでいる。夏も盛りになると、ラクビーボールの形をした西瓜も並ぶはずだ。
いまのおすすめは烏骨鶏の卵と古代米。烏骨鶏の卵は1パック4個入りで480円。これが高いのか安いのかはわからない。
待ち時間も楽しい、しなの鉄道は戸倉駅。
2011年06月22日
麦秋という名の夏
夏至を迎え、3月頃からの季節の揺らぎがようやく夏に落着いた。
麦秋という収穫の秋(とき)は初夏の新しい発見である。

教科書に載っていた二毛作。

あるいは、米の転作としての麦づくりなのかもしれない。

麦のストローを想うと、初夏の季語であることに納得した。

麦秋という収穫の秋(とき)は初夏の新しい発見である。
教科書に載っていた二毛作。
あるいは、米の転作としての麦づくりなのかもしれない。
麦のストローを想うと、初夏の季語であることに納得した。
2011年06月19日
歴史探訪、平城京から見た信濃
長野市・金鵄会館で、古代史の講演会があった。金鵄会館は国の登録有形文化財。1939(昭和14)年の建設なので「帝冠様式」に括られるだろうか。歴史の講演会に相応しい威厳と重厚な雰囲気が漂う。

正確にいうと講演会ではなく、この日は生涯学習としての「公開講座」で、『古典を読むー歴史と文学』「いま明かされる古代」が正式名称である。受講には、事前の申し込みが必要で、今回、運良く受講することができた。
会場の大教室は、学習意欲に溢れた市民の皆さんで満員である。60歳を超えた皆さんが多く、僕は若いほうだ。

この日の講義は、奈良文化財研究所の馬場基主任研究員による「信濃への都からのまなざし〜平城京と信濃」。
馬場さんは、平城京跡から出土した木簡の調査/分析により、奈良時代の社会と生活の実態を解明している。出土した木簡は、35万点以上にも及ぶ。馬場さんは、文献史料と、それを補う木簡史料を適切に関係づけ、そこに多少のイマジネーションを加えて、当時の歴史像を構築しているそうだ。そのイマジネーションが僕らの既成概念を揺さぶり、飛び越えて、実に明快で面白い。

平城京は、日本各地から「ひと」「もの」「情報」があつまる場所であった。
平城京での「信濃なるもの」の代表は「鮭」ということである。信濃というと「馬」というイメージがあったが、木簡や「延喜式」の産品を調べると、意外に「馬」は登場せず、「鮭」がこの時代の信濃の特産物として、平城京では認識されている。近代以前に動物性たんぱく質が豊富に採れることは重要なことであり、善光寺平の地域的な特性を考えるには、「鮭」がキーワードになるというお話であった。
千曲川で鮭が当たり前に採れるということを、僕らの世代は知らない。そういえば、八幡神社の例祭のときに、「鮭」を供えたことを思い出した。この風習は鮭文化の名残りだろうか。

出土した膨大な木簡はデジタル化され、データベースになって、奈文研で公開されている。その気になれば、誰でも貴重な資料にアクセスし、調査・分析することが可能な時代になった。
帰り際、ご近所の方にお会いした。『続日本紀』から運脚(律令時代,調や庸の貢納品を都まで運んだ農民)の史料を丹念に収集しているそうである。講義の冒頭、信濃の歴史研究は侮れない、今日は緊張していますという和田さんの言葉が頭をよぎった。
次回は、平安時代の受領について、そして、7月16日には、屋代から出土した7世紀木簡の講義がある。信州の古代も熱い。
『古典を読むー歴史と文学』「いま明かされる古代」
・「信濃への都からのまなざし〜平城京と信濃〜」
奈良文化財研究所 都城発掘調査部史料研究室
主任研究員 馬場 基

正確にいうと講演会ではなく、この日は生涯学習としての「公開講座」で、『古典を読むー歴史と文学』「いま明かされる古代」が正式名称である。受講には、事前の申し込みが必要で、今回、運良く受講することができた。
会場の大教室は、学習意欲に溢れた市民の皆さんで満員である。60歳を超えた皆さんが多く、僕は若いほうだ。
この日の講義は、奈良文化財研究所の馬場基主任研究員による「信濃への都からのまなざし〜平城京と信濃」。
馬場さんは、平城京跡から出土した木簡の調査/分析により、奈良時代の社会と生活の実態を解明している。出土した木簡は、35万点以上にも及ぶ。馬場さんは、文献史料と、それを補う木簡史料を適切に関係づけ、そこに多少のイマジネーションを加えて、当時の歴史像を構築しているそうだ。そのイマジネーションが僕らの既成概念を揺さぶり、飛び越えて、実に明快で面白い。
平城京は、日本各地から「ひと」「もの」「情報」があつまる場所であった。
平城京での「信濃なるもの」の代表は「鮭」ということである。信濃というと「馬」というイメージがあったが、木簡や「延喜式」の産品を調べると、意外に「馬」は登場せず、「鮭」がこの時代の信濃の特産物として、平城京では認識されている。近代以前に動物性たんぱく質が豊富に採れることは重要なことであり、善光寺平の地域的な特性を考えるには、「鮭」がキーワードになるというお話であった。
千曲川で鮭が当たり前に採れるということを、僕らの世代は知らない。そういえば、八幡神社の例祭のときに、「鮭」を供えたことを思い出した。この風習は鮭文化の名残りだろうか。
出土した膨大な木簡はデジタル化され、データベースになって、奈文研で公開されている。その気になれば、誰でも貴重な資料にアクセスし、調査・分析することが可能な時代になった。
帰り際、ご近所の方にお会いした。『続日本紀』から運脚(律令時代,調や庸の貢納品を都まで運んだ農民)の史料を丹念に収集しているそうである。講義の冒頭、信濃の歴史研究は侮れない、今日は緊張していますという和田さんの言葉が頭をよぎった。
次回は、平安時代の受領について、そして、7月16日には、屋代から出土した7世紀木簡の講義がある。信州の古代も熱い。
『古典を読むー歴史と文学』「いま明かされる古代」
・「信濃への都からのまなざし〜平城京と信濃〜」
奈良文化財研究所 都城発掘調査部史料研究室
主任研究員 馬場 基
2011年06月18日
アコースティックな夜、下山亮平
昨年の夏から、アコースティックギターの音色に魅せられている。
群馬県六合村野反湖畔のフィールドフォークに出かけてからだ。

長野市 deko cafe で下山亮平のライブがあった。
deko cafeは、アンティークな家具に包まれたレトロな雰囲気の漂うお店。段ボール工場を時間をかけて改造したそうで、手づくり感に包まれ、ゆったりとした時間が流れる。
自家菜園の有機野菜やハーブを使った料理やドリンクも用意されている。

ライブの主催者は、地元の学校の先生。松本で下山亮平に出会って以来のファンで、decocafeのレトロな空間で、下山亮平のアコースティックギターを聴きたくて、このライブを企画した。
この夜は、3rdアルバム"Philosoper's Stone"発売記念ライブ。

ウォーター・ロード・ギター。 群馬県のギター製作家増田明夫さんの手になるもの。
楽曲の創作のきっかけを語りながら演奏をしてくれるので、曲の中にすっと入り込んでその情景が目に浮かんでくる。
会社の同僚阿漕君は、野反湖で下山亮平を見初め、そのインスト音楽に戦慄してから6年ぶりの再開を果たした。
アンコールの曲は、阿漕君が野反湖で戦慄を覚えたという「神の木」。数年ぶりの演奏だそうだが、下山さんには阿漕君の思いをしっかり受け止めて、演奏してくれた。
繊細な演奏、情景が浮かんでくる楽曲、静かな情熱が伝わってくる語り。そして、さまざな人との出会いと思いが交錯するアコースティックな夜でした。

下山亮平(しもやまりょうへい)
アコースティック・ギタリスト。
山形県山形市生まれ。東京都 在住。
13歳でギターを手にする。 初めは、James Taylor、Neil Yong、C,S&Nなどのアコースティック・ギター・サウンドに興味を持ち、その後アメリカやイギリスの'70年代のロックやポップ・ミュージックに惹かれ、音楽的ルーツとなる。
またジャズ・ピアニストのBill Evansがきっかけで、ジャズに興味を持ち、影響を受ける。
主に、変則チューニングを使ったソロ・ギターのインスト曲を作曲/編曲し、演奏している。
http://r-shimoyama.guitarfreak.net/musics/index.html

群馬県六合村野反湖畔のフィールドフォークに出かけてからだ。
長野市 deko cafe で下山亮平のライブがあった。
deko cafeは、アンティークな家具に包まれたレトロな雰囲気の漂うお店。段ボール工場を時間をかけて改造したそうで、手づくり感に包まれ、ゆったりとした時間が流れる。
自家菜園の有機野菜やハーブを使った料理やドリンクも用意されている。
ライブの主催者は、地元の学校の先生。松本で下山亮平に出会って以来のファンで、decocafeのレトロな空間で、下山亮平のアコースティックギターを聴きたくて、このライブを企画した。
この夜は、3rdアルバム"Philosoper's Stone"発売記念ライブ。
ウォーター・ロード・ギター。 群馬県のギター製作家増田明夫さんの手になるもの。
楽曲の創作のきっかけを語りながら演奏をしてくれるので、曲の中にすっと入り込んでその情景が目に浮かんでくる。
会社の同僚阿漕君は、野反湖で下山亮平を見初め、そのインスト音楽に戦慄してから6年ぶりの再開を果たした。
アンコールの曲は、阿漕君が野反湖で戦慄を覚えたという「神の木」。数年ぶりの演奏だそうだが、下山さんには阿漕君の思いをしっかり受け止めて、演奏してくれた。
繊細な演奏、情景が浮かんでくる楽曲、静かな情熱が伝わってくる語り。そして、さまざな人との出会いと思いが交錯するアコースティックな夜でした。
下山亮平(しもやまりょうへい)
アコースティック・ギタリスト。
山形県山形市生まれ。東京都 在住。
13歳でギターを手にする。 初めは、James Taylor、Neil Yong、C,S&Nなどのアコースティック・ギター・サウンドに興味を持ち、その後アメリカやイギリスの'70年代のロックやポップ・ミュージックに惹かれ、音楽的ルーツとなる。
またジャズ・ピアニストのBill Evansがきっかけで、ジャズに興味を持ち、影響を受ける。
主に、変則チューニングを使ったソロ・ギターのインスト曲を作曲/編曲し、演奏している。
http://r-shimoyama.guitarfreak.net/musics/index.html
2011年06月16日
ワイン葡萄の花ごしらえ
麦秋、初夏の季語。
この時期、麦は穂が黄色くなり、収穫の秋(とき)を迎えている。

庭先のワイン葡萄の花が咲いた。
今年はまだ、実をつけない予定でいるが、少しばかり心が揺らぐ。
花きりをして、形だけでも整えてやろうと思うのである。

実は付けないと言いながら、秋にはどのような実を付けるだろうかと盛んに想像している。
ここにも秋が来ている。

花きりのことを、花ごしらえという。
まだ、若く、弱々しい樹じゃないか。切り捨てるのではなく、こしらえている途上だ。自重しよう。
この時期、麦は穂が黄色くなり、収穫の秋(とき)を迎えている。
庭先のワイン葡萄の花が咲いた。
今年はまだ、実をつけない予定でいるが、少しばかり心が揺らぐ。
花きりをして、形だけでも整えてやろうと思うのである。
実は付けないと言いながら、秋にはどのような実を付けるだろうかと盛んに想像している。
ここにも秋が来ている。
花きりのことを、花ごしらえという。
まだ、若く、弱々しい樹じゃないか。切り捨てるのではなく、こしらえている途上だ。自重しよう。
2011年06月15日
有機やさいの店、ずくなし
ギガンジウム。名もなき花の立派な名前です。
実家でこの花を栽培していたという拙ブログの読者に教えていただきました。

店先の「さくらんぼ」が目に飛び込んできて、思わず、引き返し、購入しました。これで400円。
多少不揃いではありますが、それが有機栽培の良さですね。
街角で見つけた有機やさいのお店は、「ずくなし」。

ネット販売が主体のお店のようです。有機やさいの料理も提供しています。お店の中には、ガラス壜にはいった「トッカン」があったり、懐かし楽しそうな雰囲気です。一度、ゆっくり訪ねてみることにします。


ずくなしでは出来そうにない、勇気ある挑戦ですね。

実家でこの花を栽培していたという拙ブログの読者に教えていただきました。
店先の「さくらんぼ」が目に飛び込んできて、思わず、引き返し、購入しました。これで400円。
多少不揃いではありますが、それが有機栽培の良さですね。
街角で見つけた有機やさいのお店は、「ずくなし」。
ネット販売が主体のお店のようです。有機やさいの料理も提供しています。お店の中には、ガラス壜にはいった「トッカン」があったり、懐かし楽しそうな雰囲気です。一度、ゆっくり訪ねてみることにします。
ずくなしでは出来そうにない、勇気ある挑戦ですね。
2011年06月14日
2011年06月13日
名もなき花
名もなき花ではない。
たぶん名前はあるんでしょうが、僕が知らないだけです。

ねぎ坊主だろうか、玉葱畑に咲いていた。観賞用の花だと思うが、野菜の花もそれはそれで飾り気のなさに惹かれるものがある。
庭先にある、フワ〜とした脱力感を感じる、たぶん花なんだろう。ねむの木ではないよね。ご近所にもあったので、少し安心する。


蜜蜂がさかんに蜜を取っている小さな花。花が小さくて、忙しく飛びまわる働き蜂。えらいな君は。

己の無知なることを花に教えられ、働き蜂に我が身を正す。休日の僕
たぶん名前はあるんでしょうが、僕が知らないだけです。
ねぎ坊主だろうか、玉葱畑に咲いていた。観賞用の花だと思うが、野菜の花もそれはそれで飾り気のなさに惹かれるものがある。
庭先にある、フワ〜とした脱力感を感じる、たぶん花なんだろう。ねむの木ではないよね。ご近所にもあったので、少し安心する。
蜜蜂がさかんに蜜を取っている小さな花。花が小さくて、忙しく飛びまわる働き蜂。えらいな君は。
己の無知なることを花に教えられ、働き蜂に我が身を正す。休日の僕
2011年06月12日
ご近所花探訪、薔薇
近所を自転車で走ると、薔薇の花が庭先から目に飛び込んでくる。
近づくと、甘い香りが漂う。


薔薇を植えているお宅が多いことに、改めて驚く。
薔薇は勢いがあって、どんどん植生を広げていく。僕のところでも、3年も経つと立派なアーチができて、5年を過ぎると多少持て余すようになり、いまは、小さなものだけが残っている。


育てやすいし、花はきれいで、香りも佳い。
でも、きれいな薔薇には刺があるのです。刺の痛さにめげることなく、丹精を込めたご近所に敬意。


我が家に残った薔薇。花は可憐だが、幾多の切込みにも耐える生命力。

近づくと、甘い香りが漂う。
薔薇を植えているお宅が多いことに、改めて驚く。
薔薇は勢いがあって、どんどん植生を広げていく。僕のところでも、3年も経つと立派なアーチができて、5年を過ぎると多少持て余すようになり、いまは、小さなものだけが残っている。
育てやすいし、花はきれいで、香りも佳い。
でも、きれいな薔薇には刺があるのです。刺の痛さにめげることなく、丹精を込めたご近所に敬意。
我が家に残った薔薇。花は可憐だが、幾多の切込みにも耐える生命力。
2011年06月08日
善光寺路地裏、番外編
さわやか信州な日である。
空が澄んでいる。心地佳い風がある。じめじめしていないのが、さわやか信州の成立要件。

大正ロマン漂うTHE FUJIYA GOHONJINのパティシエの造るロールケーキが隠れるように売られている。
ペコちゃんではない、「御本陣藤屋」である。
江戸の創業以来、歴代当主により襲名されてきたのが、「平五郎」。
その名を店名にした菓子屋がある。SWEETS SHOP 平五郎である。

数量限定で販売される「藤ロール」は、信州の食材をふんだんに使用したこだわりの一品。
「オブセ牛乳」、鈴木養蜂場の「菜の花ハチミツ」、小麦粉も卵も地元のものが厳選されている。
一本1,050円。カット売りも始めたようなので、平五郎を見つけたら、ぜひ味わっていただきたい。

平五郎を少し、東に入ったところに。不思議なドアがある。
そこへ昇りそこから降りる階段はなく、赤いドアが壁にはり付いている。
ドアを開けて一歩踏み出すと、それは天国への扉になっちまう。
Knockin' on heaven's door
http://bit.ly/j9KQsA
そして、菖蒲湯の時期であることを思い出させてくれた善光寺の路地裏。

空が澄んでいる。心地佳い風がある。じめじめしていないのが、さわやか信州の成立要件。
大正ロマン漂うTHE FUJIYA GOHONJINのパティシエの造るロールケーキが隠れるように売られている。
ペコちゃんではない、「御本陣藤屋」である。
江戸の創業以来、歴代当主により襲名されてきたのが、「平五郎」。
その名を店名にした菓子屋がある。SWEETS SHOP 平五郎である。
数量限定で販売される「藤ロール」は、信州の食材をふんだんに使用したこだわりの一品。
「オブセ牛乳」、鈴木養蜂場の「菜の花ハチミツ」、小麦粉も卵も地元のものが厳選されている。
一本1,050円。カット売りも始めたようなので、平五郎を見つけたら、ぜひ味わっていただきたい。
平五郎を少し、東に入ったところに。不思議なドアがある。
そこへ昇りそこから降りる階段はなく、赤いドアが壁にはり付いている。
ドアを開けて一歩踏み出すと、それは天国への扉になっちまう。
Knockin' on heaven's door
http://bit.ly/j9KQsA
そして、菖蒲湯の時期であることを思い出させてくれた善光寺の路地裏。
2011年06月07日
善光寺路地裏、再発見
善光寺の参道を外れると、面白い発見がある。

高札前の七味唐辛子と言えば、「八幡屋礒五郎」で有名だが、同じくらいのポテンシャルを秘めていると思われるのが、「三河屋庄左衛門」だ。商いは「水油」。
江戸時代中頃からの菜種油製造問屋で水油=菜種油や蠟燭を扱っていたそうだ。善光寺の参道から東に入る「東町」にコンクリート打ちっ放しのモダンな店を構えている。

旧い商家は、1847(弘化4)年の善光寺地震後、再建されたもので、幕末の佇まいを現在に伝え、「門前商家 ちょっ蔵おいらい館」として開放されている。
入り口には、商人風の人形が当時の帳場を再現している。

蔵はギャラリーになっている。静かで落着く場所だ。裏手には、大きなお寺の屋根が見える。


現在のご商売は、胡麻製品。胡麻の産地はどこか、わからないが、長野県産であればうれしい。
八幡屋礒五郎と「三河屋庄左衛門」とが、軒を連ねていると素敵だな。

善光寺さん参拝の往きは中央通で、復路は路地裏を巡って、権堂に抜けるルートがあってもいい。三河屋さんの先には、休日には、行列ができているおにぎりの専門店もある。
権堂の裏通りは寂れているが、旅する人の視点からは面白い発見もあるかもしれない。

三河屋さんの信号を北に向かうと、再生された古いビニール傘の工場が、洒落たお店になっている。
一度、ゆっくり訪ねてみたい。
高札前の七味唐辛子と言えば、「八幡屋礒五郎」で有名だが、同じくらいのポテンシャルを秘めていると思われるのが、「三河屋庄左衛門」だ。商いは「水油」。
江戸時代中頃からの菜種油製造問屋で水油=菜種油や蠟燭を扱っていたそうだ。善光寺の参道から東に入る「東町」にコンクリート打ちっ放しのモダンな店を構えている。
旧い商家は、1847(弘化4)年の善光寺地震後、再建されたもので、幕末の佇まいを現在に伝え、「門前商家 ちょっ蔵おいらい館」として開放されている。
入り口には、商人風の人形が当時の帳場を再現している。
蔵はギャラリーになっている。静かで落着く場所だ。裏手には、大きなお寺の屋根が見える。
現在のご商売は、胡麻製品。胡麻の産地はどこか、わからないが、長野県産であればうれしい。
八幡屋礒五郎と「三河屋庄左衛門」とが、軒を連ねていると素敵だな。
善光寺さん参拝の往きは中央通で、復路は路地裏を巡って、権堂に抜けるルートがあってもいい。三河屋さんの先には、休日には、行列ができているおにぎりの専門店もある。
権堂の裏通りは寂れているが、旅する人の視点からは面白い発見もあるかもしれない。
三河屋さんの信号を北に向かうと、再生された古いビニール傘の工場が、洒落たお店になっている。
一度、ゆっくり訪ねてみたい。
2011年06月06日
一心堂餅店、石臼挽き団子
心地よい風が窓から通り過ぎる。いつ頃まで、冷房なしでいけるだろうか。

きき酒のトレーニングのため、「西之門」で試飲をさせていただいた。
吟醸、原酒、純米酒、そして、本醸造。それぞれに確かに違うな。「純米酒」の口当たりが、先日のきき酒、混乱の原因だった。ここの純米酒は酸味強い感じがする。違いのわかる男を鍛えていこう。

西之門の通りを西に入って、「一心堂餅店」で団子をいただく。
ここでは、飯山市木島のコシヒカリを石臼で挽き、その日の朝、団子にする。
「コシヒカリ石臼挽き団子」
珍しいので抹茶、そして定番の醤油をいただく。
ここの団子は円筒形。長く棒状に伸ばしたものをだんごの大きさに裁るのだろう。

大福、豆餅も、その日に搗いたものが並ぶ。もち米は「飯山市木島産のこがねもち」
定番とは別に季節を感じる和菓子も。「かしわ餅」が出ていた。つい先ごろまでは、「道明寺」。
お気に入りは「麩饅頭」。季節はいつだったかな。
「一心堂餅店」。売切れ終了なので、午前中がよいかも。8時から開いてます。
http://www.avis.ne.jp/~fuu/

きき酒のトレーニングのため、「西之門」で試飲をさせていただいた。
吟醸、原酒、純米酒、そして、本醸造。それぞれに確かに違うな。「純米酒」の口当たりが、先日のきき酒、混乱の原因だった。ここの純米酒は酸味強い感じがする。違いのわかる男を鍛えていこう。
西之門の通りを西に入って、「一心堂餅店」で団子をいただく。
ここでは、飯山市木島のコシヒカリを石臼で挽き、その日の朝、団子にする。
「コシヒカリ石臼挽き団子」
珍しいので抹茶、そして定番の醤油をいただく。
ここの団子は円筒形。長く棒状に伸ばしたものをだんごの大きさに裁るのだろう。
大福、豆餅も、その日に搗いたものが並ぶ。もち米は「飯山市木島産のこがねもち」
定番とは別に季節を感じる和菓子も。「かしわ餅」が出ていた。つい先ごろまでは、「道明寺」。
お気に入りは「麩饅頭」。季節はいつだったかな。
「一心堂餅店」。売切れ終了なので、午前中がよいかも。8時から開いてます。
http://www.avis.ne.jp/~fuu/
2011年06月05日
きき酒大会、傾向と対策
全国きき酒選手権大会の長野/中野地区予選会が長野市のメルパルクで行われました。
この予選の上位者は、松本市の県予選に出場です。
日頃、鍛えているきき酒の腕(舌でしょうか)を試そうと、集まった日本酒を愛する皆さんは60名あまり。

きき酒の方法です。
2つのテーブルに、それぞれ6種類の日本酒が置いてあります。日本酒は、吟醸、本醸、純米、原酒、甘口、辛口の6種類です。当日は、「水尾」の飯山市田中屋醸造店の提供でした。

第一のテーブルの瓶には、A〜Fのラベルが貼られています。きき猪口に少しずつ、酒を注ぎ、色を見て、香りを嗅いで、口に含んで、僕の場合は、ゴクリ。6種類の酒の味わいを確かめ、自分の好みの順に「嗜好順位」をつけます。制限時間は5分。
第二のテーブルに移ります。瓶にはイロハニホヘのラベルが貼られています。この時点で、6種類の酒は、シャッフルされてしまったわけです。ここでも、きき猪口で酒を確かめ、嗜好順位をつけます。
このきき酒大会は、日本酒の種類を当てるのではなく、本人の嗜好の確かさ、つまり味覚の感度が問われることになります。
採点は、二つのテーブルの嗜好順位が合致しているかどうかを基準に行われます。

第一テーブルで、6種類の酒の印象を記憶(寸評として記録)するのですが、はっきり認識できたのが、3種類。半分は、特徴が掴めませんでした。5分という時間に急かされるように、第二テーブルへ移動。はじめに手にした酒の印象が、第一テーブルにはなかったような味。ウ〜〜ン、これは弱った。つぎも「記憶にございません」。とにかく、認識できた3種類を見つけようと焦り始めました。結局、これだなと「嗜好」が合致したものは、一つだけでした。メンタルが安定してないと、味覚って何処かへ飛んでしまうものですね。
メンタル弱いんだなと、きき酒会でメンタルチェックをしている自分が情けない。
気を取り直して、隣の会場で、長野/中野酒造組合の酒蔵の皆さんの、新酒を賞味することに。こちらでは、自慢の新酒を酒蔵の皆さんからお話を聞きながら、頂戴しました。

中野酒造組合会長の丸世酒造店関社長に「旭の出乃勢正宗 もち米熱掛四段純米原酒」を注いでいただき、こっそりと「きき酒攻略法」を伝授していただきました。
・採点は、第二回めの嗜好順位(a)から、対応する一回めの嗜好順位(b)の差を出す。aーb=(c)、この(c)の値を2乗する。
・イのラベルの嗜好順位が5番(a)とし、イのラベルに相当する第一回めの酒をBのラベルの嗜好順位を対応させる。Bラベルを5番(b)としていれば、5−5=0点。嗜好が完全一致していれば、0点が満点である。
・差額を2乗するのだから、順位差が1であれば、1点。順位差が2であれば、4点。順位差が3であれば、9点になる。
・仮に、順位を真逆につけてしまった場合、第一テーブルの1位〜6位が、第二テーブル6位〜1位になったケース、それはそれで凄いことだが、得点は70点になる。
・ポイントは、順位差を少なくすること。傾向の同じものを集めて、順位をつけること。
来年も、開催するとのことですので、この攻略法でリベンジを期します。僕の場合は、その前にメンタルトレーニングですが。
予選会の優勝者の得点は、「2点」でした。この方は、アルコールの強さで順位を点けたそうです。或る意味、繊細な舌の感覚があるんだな。僕の場合は、アルコールの強弱は麻痺していますからね。
人それぞれ、自分の好みがあるでしょうが、明確な基準を持ち、その基準を記憶し、同傾向のものをグルーピングし、順位付けができた人が良い成績につながる。

僕と同じグループ(6人組)から、準優勝者と第3位が輩出。3位の「藤岡有機農園」の藤岡さん。1979年より地球環境、こどもたちの未来のことを考え、有機農業を実践しているそうです。このこだわりが好成績に結びつく。
僕にとっては、頂戴した新酒が、一晩明けても効いている「きき酒会」でした。

「本老の松」の東飯田酒造店の看板娘。秋の酒メッセでのコスプレにも期待。
この予選の上位者は、松本市の県予選に出場です。
日頃、鍛えているきき酒の腕(舌でしょうか)を試そうと、集まった日本酒を愛する皆さんは60名あまり。
きき酒の方法です。
2つのテーブルに、それぞれ6種類の日本酒が置いてあります。日本酒は、吟醸、本醸、純米、原酒、甘口、辛口の6種類です。当日は、「水尾」の飯山市田中屋醸造店の提供でした。
第一のテーブルの瓶には、A〜Fのラベルが貼られています。きき猪口に少しずつ、酒を注ぎ、色を見て、香りを嗅いで、口に含んで、僕の場合は、ゴクリ。6種類の酒の味わいを確かめ、自分の好みの順に「嗜好順位」をつけます。制限時間は5分。
第二のテーブルに移ります。瓶にはイロハニホヘのラベルが貼られています。この時点で、6種類の酒は、シャッフルされてしまったわけです。ここでも、きき猪口で酒を確かめ、嗜好順位をつけます。
このきき酒大会は、日本酒の種類を当てるのではなく、本人の嗜好の確かさ、つまり味覚の感度が問われることになります。
採点は、二つのテーブルの嗜好順位が合致しているかどうかを基準に行われます。
第一テーブルで、6種類の酒の印象を記憶(寸評として記録)するのですが、はっきり認識できたのが、3種類。半分は、特徴が掴めませんでした。5分という時間に急かされるように、第二テーブルへ移動。はじめに手にした酒の印象が、第一テーブルにはなかったような味。ウ〜〜ン、これは弱った。つぎも「記憶にございません」。とにかく、認識できた3種類を見つけようと焦り始めました。結局、これだなと「嗜好」が合致したものは、一つだけでした。メンタルが安定してないと、味覚って何処かへ飛んでしまうものですね。
メンタル弱いんだなと、きき酒会でメンタルチェックをしている自分が情けない。
気を取り直して、隣の会場で、長野/中野酒造組合の酒蔵の皆さんの、新酒を賞味することに。こちらでは、自慢の新酒を酒蔵の皆さんからお話を聞きながら、頂戴しました。
中野酒造組合会長の丸世酒造店関社長に「旭の出乃勢正宗 もち米熱掛四段純米原酒」を注いでいただき、こっそりと「きき酒攻略法」を伝授していただきました。
・採点は、第二回めの嗜好順位(a)から、対応する一回めの嗜好順位(b)の差を出す。aーb=(c)、この(c)の値を2乗する。
・イのラベルの嗜好順位が5番(a)とし、イのラベルに相当する第一回めの酒をBのラベルの嗜好順位を対応させる。Bラベルを5番(b)としていれば、5−5=0点。嗜好が完全一致していれば、0点が満点である。
・差額を2乗するのだから、順位差が1であれば、1点。順位差が2であれば、4点。順位差が3であれば、9点になる。
・仮に、順位を真逆につけてしまった場合、第一テーブルの1位〜6位が、第二テーブル6位〜1位になったケース、それはそれで凄いことだが、得点は70点になる。
・ポイントは、順位差を少なくすること。傾向の同じものを集めて、順位をつけること。
来年も、開催するとのことですので、この攻略法でリベンジを期します。僕の場合は、その前にメンタルトレーニングですが。
予選会の優勝者の得点は、「2点」でした。この方は、アルコールの強さで順位を点けたそうです。或る意味、繊細な舌の感覚があるんだな。僕の場合は、アルコールの強弱は麻痺していますからね。
人それぞれ、自分の好みがあるでしょうが、明確な基準を持ち、その基準を記憶し、同傾向のものをグルーピングし、順位付けができた人が良い成績につながる。
僕と同じグループ(6人組)から、準優勝者と第3位が輩出。3位の「藤岡有機農園」の藤岡さん。1979年より地球環境、こどもたちの未来のことを考え、有機農業を実践しているそうです。このこだわりが好成績に結びつく。
僕にとっては、頂戴した新酒が、一晩明けても効いている「きき酒会」でした。
「本老の松」の東飯田酒造店の看板娘。秋の酒メッセでのコスプレにも期待。